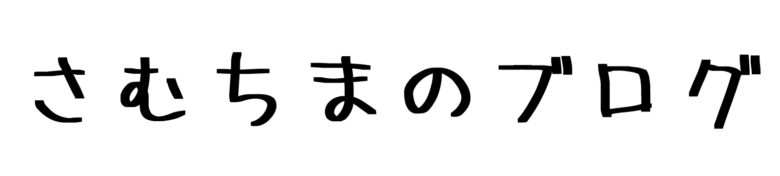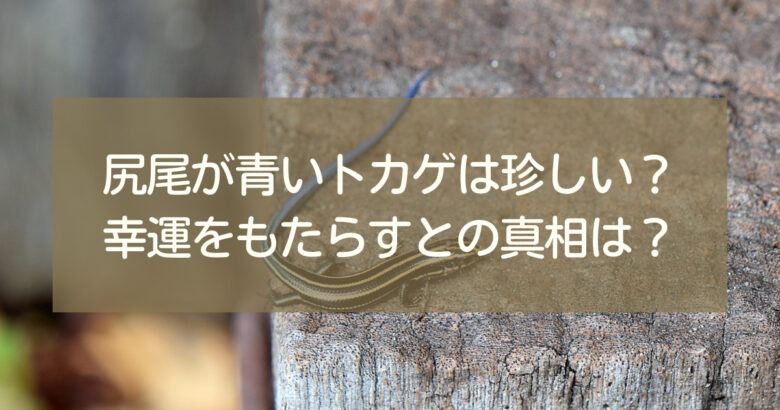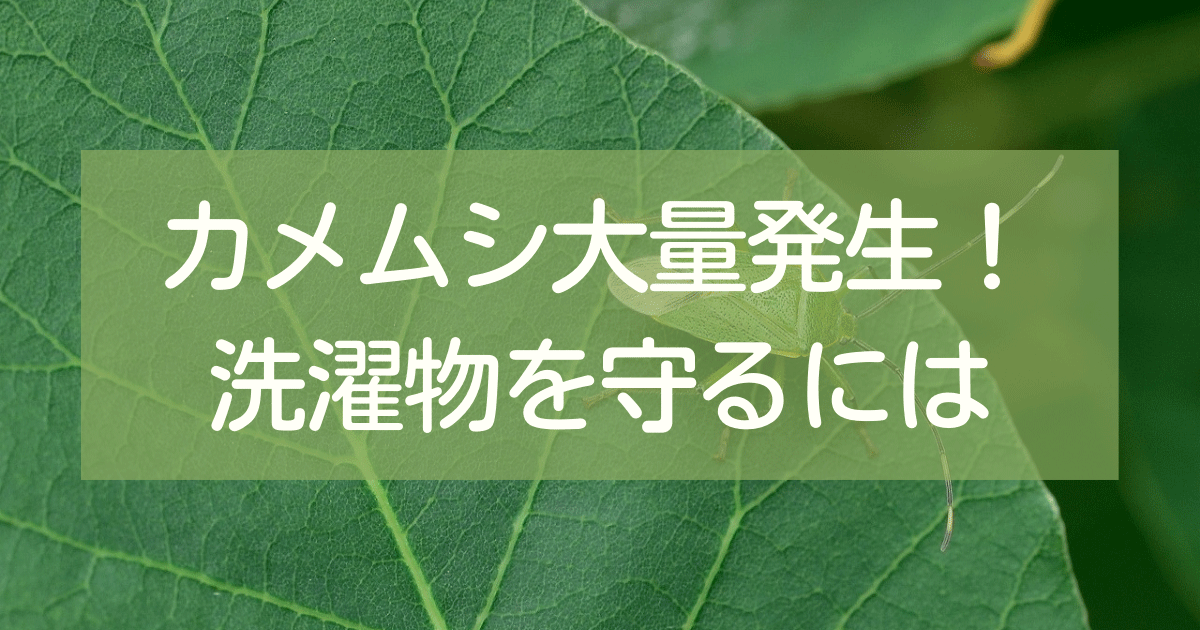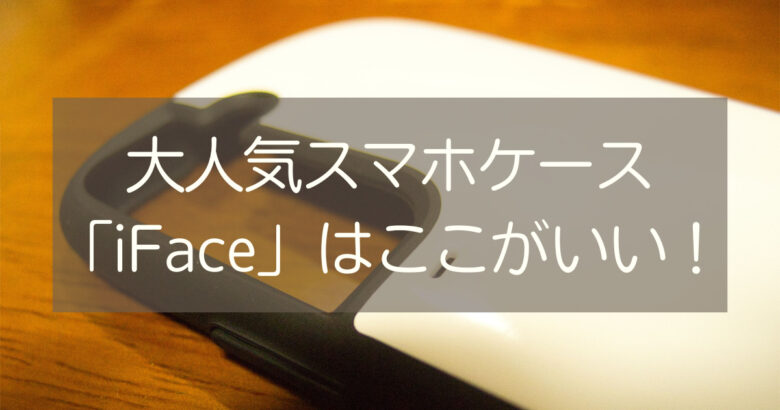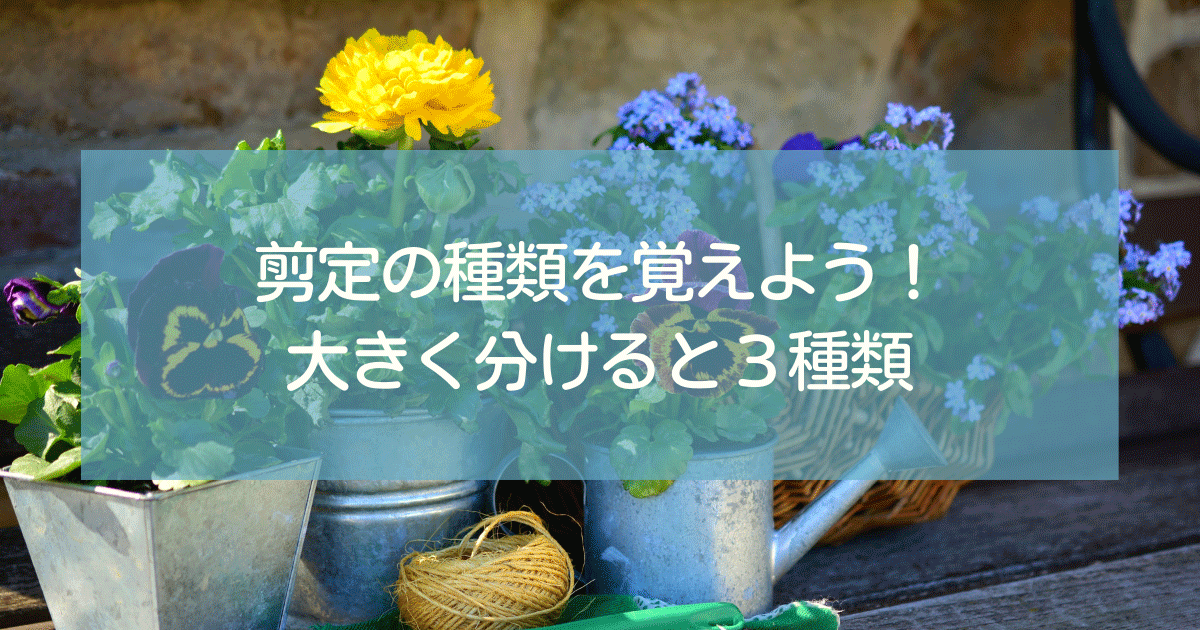大きくなってきた木を短く切るのが剪定だと思っていました。
でも、勉強していくうちに
- 剪定には種類がある
- それぞれに異なった目的がある
ことを知るようになりました。
ただ短く切るのと、目的を持って剪定していくのとでは、モチベーションが変わりますよね!どうせやるなら楽しんでやりたい。
この記事では、大きく分けて3種類といわれる剪定の基本について、調べていてわかったことをまとめていきたいと思います。
透かし剪定
透かし剪定の目的は、混み合っている枝や葉の数を減らし、風通しや日当たりを良くすることです。
植物が育ってくると、中には方向の悪い枝が出てきたり、同じところから何本も枝が出て混み合ってしまうことがあります。これが植物の成長に良くない影響を与えることがあるんですね。
- 日が当たらない → しっかりと光合成ができない
- 風通しが悪い → 内部が蒸れて病気になりやすい
それゆえ、透かし剪定をする目的は、植物を健康的に育てるために行ないます。
枝の途中で切ってしまうと、そこからまた枝分かれして増えてしまうので、透かし剪定をする場合は「枝の根元からしっかり切る」ことが基本です。
この基本を知っただけで、剪定がうんと楽しくなりました。作業が大変なことはあるんですけど、「何のためにやっているのか」、「この先どうなっていくのか」が意識できるようになってきましたからね。
これまで知らずに切っていた悪いところも発見できるようになりました。
切り残しのことを「おつり」というらしいのですが、おつりもサッパリと綺麗にできるようになり、いい感じになってきました!
切り戻し剪定
切り戻し剪定の目的は大きく分けて2つあります。
- 伸びすぎた枝を短くして樹形を整える
- 開花を促進する、または枝数を増やす
伸びすぎた枝は半分~1/3あたりでカットすることによって、木が大きくなりすぎないように樹形を保っていくことができます。
枝を切ったところからは、新しい枝が枝分かれして増えるため、全体の枝数を増やすことができます。また、切り口より先には栄養がいかなくなるため、大きく育てたい芽の少し上で切り、十分な栄養を与えるということも行ないます。
植物がまだ新しいうちは、切るともったいないようですが、「大きく育てるためにあえて切る」ことで、株自体をまずしっかりと育て、樹勢をつけることができます。
この情報を知った時に、思い切ってパッツン、パッツンに切ってみたことがあるんですが、新芽がビックリするほど増えて嬉しかった覚えがあります。
植物によって剪定に適した時期と、大きく育てるために「ここを切る!」というポイントがありますので、ただ闇雲に切ってしまうのはやめましょう。
刈り込み
刈り込みは生け垣などの手入れに使われる方法で、刈り込みバサミやトリマーといった道具を使います。
頭を丸刈りにするのにバリカンを使うイメージですね。
表面はきれいに仕上がるのですが、内側で混み合っているところが残ってしまうというデメリットもあるようです。
表面がきれいに整っていても、内側が枯れてしまっている木を見たことがあるかもしれません。
対策としては、刈り込んだ後に透かし剪定を併用して風通しを良くするか、何回かに一度は内側までしっかりと手を入れて剪定すると植物が元気に育っていきます。
剪定の種類を覚えよう!大きく分けると3種類まとめ
剪定には大きく分けて
- 透かし剪定
- 切り戻し剪定
- 刈り込み
がありましたね。
それぞれに
- 日当たり、風通しを良くする
- 樹形を整える、成長を促す
- 見た目をきれいに整える
といった目的がありました。
剪定を行うときには、自分がどうしたいのかといった目的を明確にすることで、ふさわしい剪定方法を選ぶことができるようになります。